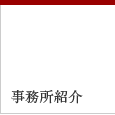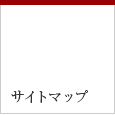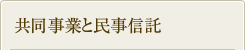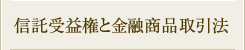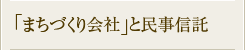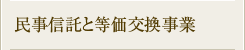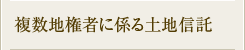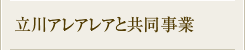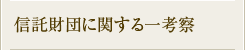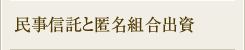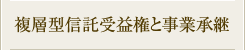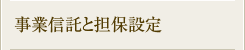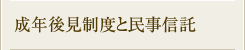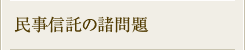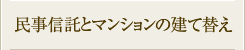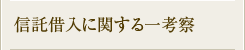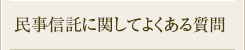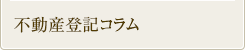昭和61年国税庁通達は、他益信託の場合受益権を譲渡しても不動産の譲渡とは認めていません(事業用資産の買換特例等の否認)。株を売って別の不動産を買ったと同じとみなします。
(注)但し、同通達は平成18年の新信託法の施行と同時に廃止となりました。今後は、各事例ごとの個別判断となります。
他益信託の事例

上記図のスキームの場合、Aの土地についてはAを委託者兼受益者、BCDを他益信託の受益者といいます。
信託財団
工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、観光施設財団、道路交通事業財団等、事業資金借り入れの担保として土地建物及び付属施設を一体として一個の不動産とみなすことができる法律があります。上記図のケースの場合、ABCDの土地を一体として一個の不動産とみなすことができれば他益信託にはなりません。
信託財団の事例-1

信託財団が認められれば、複数棟を一体とした信託財産とすることも可能となります。
信託財団にすることのメリット
- A棟B棟の空室率や賃料収入が違っても共同事業者全員が平等に二棟からの信託配当(賃料収入)を受けることができます。
- A棟B棟両棟が総合設計で有ったり、どちらかに容積移転をしている場合、公平の観念からも収益を合算して配当できることが望ましい。
信託財団の事例-2

西棟・東棟を一個の財団とすることができれば、自益信託となりかつ地権者A〜Hも二棟からの配当を平等に受けることができます。
現行法に基づいて自益信託とする事例

- 土地に設定されている個々の地権者の担保を抹消し(担保力の現出)、それぞれが取得する賃借権受益権に変わり担保として質権を設定。
- 賃借権受益権の条件:施設建築物に対する権利が付着している受益権(配当受益権)であること。
- 建築資金を捻出するため担保抹消され信託された土地に受託者が信託行為に基づき抵当権を設定(債務者は受託者)。共同事業の場合、受託者は各共同事業者が事業シェア割合で出資した会社であることが多い。
- 施設建築物の完成→所有権保存信託(受益者:各共同事業者)
-
信託の終了
・土地は元本受益権者へ戻します(信託財産の引継を原因とする所有権の移転及び信託抹消登記)。
・賃借権は、定期借地権の期間内であれば信託をはずしてもとの定期借地権の準共有に戻します(信託財産の引継を原因とする賃借権の移転及び信託抹消登記)。
・建物は各共同事業者の準共有受益権持分が所有権持分に変わります(信託財産の引継を原因とする持分移転及び信託抹消登記)。